- ※本ページはプロモーションが含まれており、当サイトは広告収入により運営されています。

ライター:西口遼
1999年生まれ、サッカー歴15年のスポーツマンWebライター。日本サッカー協会公認の指導者ライセンス保有。
サッカー少年の技術指導をおこなっています。私自身も社会人リーグでプレーする現役サッカー選手です。
現役プレーヤー兼指導者で現場に立つスポーツマンの視点で、皆様に有益な情報を発信していきます!
保有資格:日本サッカー協会公認C級コーチライセンス、高等学校教諭一種免許状(保健体育)
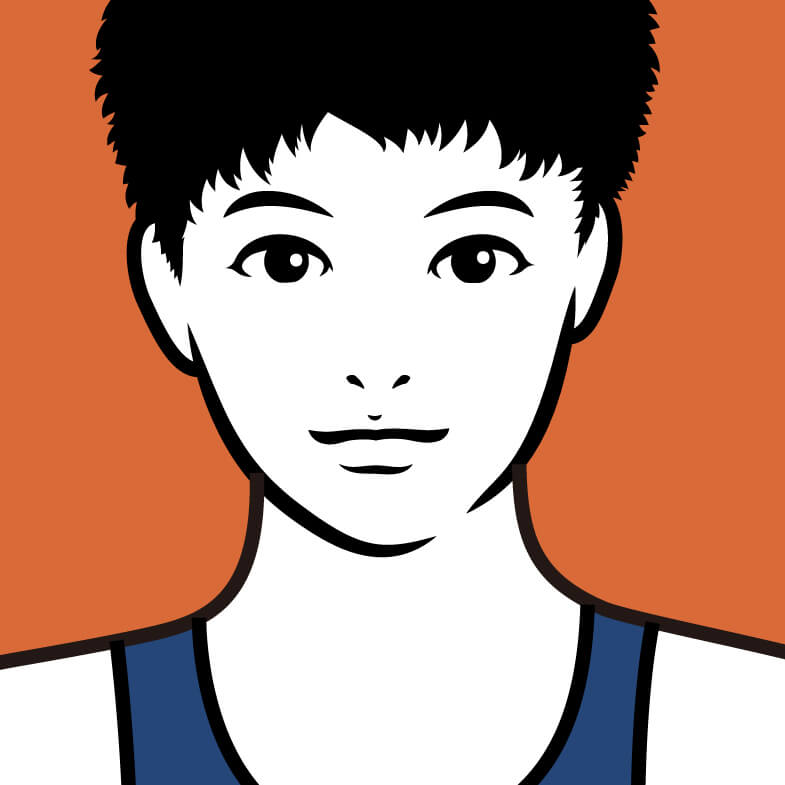
監修:michael
筋トレ歴4年の神戸市在住のパーソナルトレーナー。過去にNPCJコンテスト出場経験あり。
ダイエットや筋肥大に関する正しい知識を多くに人に理解してもらえるよう、自身の経験を交えて発信していきます。
趣味:映画鑑賞、読書、サッカー観戦
筋肉をつけたいという人の中でも特に、「胸板を厚くしてたくましい体を手に入れたい」という人は多いと思います。マッチョな海外俳優や筋骨隆々なアスリートを見ると、胸の筋肉が大きく発達していますよね。厚い胸板は、まさにマッチョの象徴とも言えます。
そこで、厚い胸板を作ってたくましい体を手に入れるために、胸筋を飛躍的に大きくする鍛え方を解説します。
今回の解説内容はこちらの3つです。
- 胸筋の基礎知識
- 効果抜群のおすすめ胸筋トレーニング
- トレーニング効果を引き出すためのコツ
目次
1.胸筋の基礎知識

胸筋の鍛え方を具体的に説明する前に、知っておいて損のない胸筋の基礎知識について簡単に解説していきます。今回解説するポイントは、次の2つです。
- 熱い胸板を手に入れたいなら大胸筋を鍛える
- 胸筋を鍛えるメリット
胸筋への基礎知識があるのとないのとでは、トレーニングでのモチベーションや細かい意識が変わってきますよ。最低限知っておくべき知識をおさえて、効果的にトレーニングをおこなっていきましょう。
1-1.厚い胸板を手に入れたいなら大胸筋を鍛える
1つ目の基礎知識は、熱い胸板を手に入れたいなら大胸筋を鍛えるということ。
胸まわりを鍛えたいと考えていても、鍛えるべき筋肉の部位と名前を知らない人は意外と多いと思います。「熱い胸板を手に入れたい」と考えている人は、胸部で最も大きい筋肉である大胸筋を鍛えましょう。大胸筋は、腕を内側に閉じたり、上に上げたりするときに働く筋肉です。
大胸筋は、細かく分解すると上部・中部・下部に分かれています。
それぞれの部位を鍛えると、どのような効果が得られるかも簡単に整理しておきましょう。
| 【大胸筋の部位】 | 【鍛えると得られる効果】 |
| 上部 | 鎖骨下あたりから、筋肉の盛り上がりを作ることができる |
| 中部 | 大胸筋を横に広くする |
| 下部 | 大胸筋の厚みを作ることができる |
大胸筋全体を大きくするなら、3つの部位をバランス良く鍛える必要があります。
トレーニングメニューを選ぶときも、大胸筋のどの部位を鍛えることができるかを意識してみましょう。
1-2.胸筋を鍛えるメリット
2つ目の基礎知識は、胸筋を鍛えるメリットについて。
トレーニングを始める前に、胸筋を鍛えるメリットについて簡単に知っておきましょう。
【胸筋を鍛えるメリット】
- 胸板が厚くなり、たくましい体になる
- 姿勢が良くなる
- 肩こりが改善する
胸筋を鍛えると胸板が厚くなるだけでなく、姿勢や肩こりの改善といった生活習慣にも良い影響があります。そもそも、猫背や肩こりは大胸筋の硬直が原因の一つ。胸筋のトレーニングは、大胸筋の硬直を防ぐために最適な方法です。
胸筋を鍛えれば、たくましい体を手に入れられるだけでなく、普段の生活でも多くの恩恵を受けることができますよ。
2.【器具なし】胸筋の鍛え方 おすすめメニュー3選

それでは、実際に胸筋の鍛え方について見ていきましょう。
ここでは、自宅でも器具なしで始めることができる自重トレーニングメニューを紹介します。今回紹介するメニューは、次の3つ。
- プッシュアップ
- デクラインプッシュ
- インクラインプッシュアップ
大きくまとめてしまえば、すべて「腕立て伏せ」のメニューです。
しかし、それぞれのメニューで鍛えられる胸筋の部位が違います。鍛えている胸筋の部位を意識しながらトレーニングに取り組みましょう。
2-1.おすすめメニュー① プッシュアップ
1つ目のおすすめメニューは、プッシュアップ。
いわゆる、通常の腕立て伏せです。プッシュアップでは、おもに大胸筋中部を鍛えることができます。
【プッシュアップのやり方】
- 四つん這いになり胸のラインに手を置く
- 手幅を肩幅の1.5倍程度に開く
- 胸を張った状態で肘を曲げて身体を下ろしていく
- 胸が地面につくくらいまで下ろしたら元の位置に戻していく
10回×3セットを目安におこないましょう。簡単な人は動作をゆっくりすること、難しい人は膝をつくことで負荷の調整ができます。きつくなってくると、お尻が上がってくる人がいますが、これは負荷が抜けるので注意しましょう。
2-2.おすすめメニュー② デクラインプッシュアップ
2つ目のメニューは、デクラインプッシュアップ。
デクラインプッシュアップは、足を高い位置に固定しておこなう腕立て伏せのことです。体を支える部分が腕だけになり、大胸筋上部を鍛えることができます。
【デクラインプッシュアップのやり方】
- 安定したベンチや椅子など、適度な高さがあるものに足を乗せる。
- 手は地面につき、腕立て伏せと同じ姿勢をつくる。
- 肘を曲げながら上体を降ろし、1秒間キープ。
- 肘を伸ばしながら上体を上げる。
10回×3セットを目安におこないましょう。頭から足先までを一直線上にキープしながら上げ下げをしましょう。
2-3.おすすめメニュー③ インクラインプッシュアップ
3つ目のメニューは、インクラインプッシュアップ。
インクラインプッシュアップは、上半身を高い位置に固定しておこなう腕立て伏せのことで、デクラインプッシュの逆です。おもに、大胸筋下部に刺激を与えることができます。
【インクラインプッシュアップのやり方】
- 安定した椅子や机などに、肩幅よりこぶし2個分広く両手をつく。
- 足を閉じて地面につけ、腕立て伏せと同じ姿勢をつくる。
- 肘を曲げながら、上体が両手につくまで下げる。
- 肘を伸ばしながら上体を上げる。
10回×3セットを目安におこない、1回1回ゆっくりおこないましょう。大胸筋が刺激を感じるところまで胸を降ろすことがポイントです。
3.【器具あり】胸筋の鍛え方 おすすめメニュー4選

次に、ジムのマシンを使ったりダンベルやバーベルを使用したりする胸筋の鍛え方を紹介します。ジムに行ける環境の人や自重トレーニングだけでは物足りなくなった人は、チャレンジしてみましょう。今回紹介するメニューは、こちらの4つ。
- ベンチプレス
- ダンベルプレス
- ディップス
- インクラインダンベルフライ
自重トレーニングに比べて器具を使ったトレーニングは、より正しいフォームを意識しないと効果が薄れてしまいます。やり方やポイントをおさえて、効果的に胸筋を鍛えていきましょう。
3-1.おすすめメニュー① ベンチプレス
1つ目のメニューは、ベンチプレス。大胸筋を鍛える定番メニューで、初心者から上級者まで全トレーニーの必須種目と言えます。
【ベンチプレスのやり方】
- ベンチに仰向けになり、肩幅の1.5倍程度広い位置でバーを握る。
- バーを握ったままブリッジを作り、脚を踏ん張れる位置にセット
- バーをラックアップし、肩の真上にセットする
- バーを胸のラインの剣状突起(みぞおちの骨)に向かって下ろす
- 前腕が地面と垂直になったら弧を描くように持ち上げる
ベンチプレスは大胸筋の中で最も高重量を扱える種目なので、1種目にもってきて8−12回程度で限界が来るような重量に設定しましょう。
ただ高重量を持ち上げれば良いのではなく大胸筋に負荷を乗せるのが重要なので、胸でバウンドさせたり、お尻を浮かせたりせず身体を固定して適切なスピードで行うのが重要です。
3-2.おすすめメニュー② ダンベルプレス
2つ目のメニューは、ダンベルプレスです。
1つ目に紹介したベンチプレスと同じ要領で、ダンベルを持ち上げるトレーニングです。
【ダンベルプレスのやり方】
- ベンチに座り、両手にダンベルを持ち、膝の上に乗せる
- 膝でダンベルを蹴り上げるようにして仰向けになり、ダンベルを肩の上にセット
- カタカナのハの字を作るようにダンベルの角度を調整し、ブリッジを組む
- ダンベルを胸のラインに向かって下ろしていく
- 前腕が地面と垂直になったら、斜め上に持ち上げる
ダンベルプレスはベンチプレスとほぼ同じ種目ですが、片腕ずつダンベルを持つので、左右対称になりづらく軌道もブレやすいです。
ただし、ダンベルの角度を調整しやすいので、ベンチプレスで手首が痛いという人はダンベルプレスの方が安全に行えます。
ベンチプレスの軌道が安定してくれば、ダンベルプレスのフォームもすぐ習得できるので挑戦してみましょう。
3-3.おすすめメニュー③ ディップス
3つ目のメニューはディップス。器具ありのメニューとして紹介していますが、工夫すれば自宅の椅子などでも代用可能です。
【ディップスのやり方】
- 平行棒を両手で掴み、身体は前傾姿勢にして後ろで足を組む
- 胸を張り身体を前傾させたまま、身体を下ろしていく
- 肘が直角になるまで下ろしたら身体を持ち上げる
- 肘が伸びきる直前で再度下ろしていく
大胸筋下部の他に上腕三頭筋、三角筋前部を動員することで高重量を扱える種目です。特に重要なポイントは前傾姿勢で、前傾させずに行うと腕が身体に対して過度に後方に位置する過伸展となり、肩の損傷につながります。
前傾姿勢を作ることで過伸展とならず肩の怪我を予防でき、大胸筋にも負荷を載せやすくなります。自重で厳しい場合はアシストの台に乗って行うようにし、逆に自重で軽い場合はダンベルやプレートを身体にぶら下げて負荷を上げていきましょう。
3-4.おすすめメニュー④ インクラインダンベルフライ
4つ目のメニューはインクラインダンベルフライ。
頭を上に固定し体を斜めに向けた状態でダンベルが円軌道を描くように行う種目です。おもに大胸筋上部を鍛えることができます。
【インクラインダンベルフライのやり方】
- 角度を30〜45°に設定したベンチに座り、ダンベルを持ち膝の上に乗せる
- 膝でダンベルを蹴り上げながらベンチに仰向けになる
- 腕を伸ばして手のひらを合わせるようにダンベルを向かい合わせる
- 4の状態で肩甲骨を寄せて肩を落とした状態で固定する
- 肘を外に開きながら弧を描くようにダンベルを下ろしていく
- ダンベルが胸の横に来たら、元の位置に弧を描くように持ち上げる
インクラインダンベルフライでは、いかに大胸筋をストレッチさせるかが重要です。スタートポジションで十分に胸を張った状態を作り、その状態のまま動作を行います。
ダンベルを下ろした時に大胸筋が外側に引っ張られるような強烈のストレッチの刺激が入り、逆にダンベルを上げるときには内側に絞られるような収縮の刺激が入ります。
ベンチプレスやディップスが物理的に高負荷で刺激を加えるのに対し、インクラインダンベルフライでは引っ張るようなストレッチの刺激が加わります。
異なる刺激を与えられる種目として、ベンチプレスやディップスの後に行うメニューとして取り入れましょう。
4.トレーニング効果を引き出すための秘訣

大胸筋を鍛える際は細かなポイントがいくつかあり、意外と誤解している人は多いです。以下で適切に大胸筋を鍛えるために意識すべきポイントを紹介していきます。
- 肩甲骨の下方回旋を意識する
- 適切な呼吸
- 軌道は斜め上を意識する
4-1.肩甲骨の下方回旋を意識する
1つ目のポイントは肩甲骨の下方回旋を意識することです。肩甲骨の下方回旋とは肩甲骨を寄せて下げた状態を意味します。
大胸筋のトレーニングでよく言われる「ブリッジを組む」を肩甲骨を寄せることだと考えている人がいますが、ブリッジは肩甲骨の下方回旋のことです。
ただ中央に寄せるだけでは胸をうまく張れないので大胸筋をうまく使えず肩の怪我にもつながります。
肩甲骨を下方回旋させることで適切なブリッジを組むことができ、肩を痛めることなく大胸筋の力をうまくバーに伝えられます。
4-2.適切な呼吸
2つ目のポイントは適切な呼吸です。大胸筋のトレーニングでは大胸筋がストレッチしていく時に吸い、収縮する時に吐きます。収縮時に大きな力を発揮するのに息を吐きながら行うと効果的です。
また、これとは別にバルサルバ法というやり方もあります。
バルサルバ法は大きく息を吸った後に息を止めた状態で種目をやるという方法です。思い切り息を吸うことで腹圧が高まり、リフティングベルトを着けた状態のように踏ん張ることができ、大きな力を発揮できます。
ただし、血圧が急上昇するので高血圧気味の人は行ってはなりません。
4-3.軌道は斜め上を意識する
3つ目は斜め上の軌道を意識することです。ベンチプレスというとバーベルが垂直に上下するイメージを持つ人が多いですが、正解は斜め上の軌道です。
バーをラックアップした状態で肩関節の真上、下ろす時は胸のラインに合う位置となります。胸より上の位置で上下するような運動になると、大胸筋が使えず肩に負荷がかかり怪我につながるので注意しましょう。
5.根気強く胸筋を鍛えてたくましい体を手に入れよう

最後に、これから胸筋を鍛えようと考えている人に最も大切なことをお伝えします。
それは、根気強くトレーニングを継続すること。筋トレは、始めてから効果が出るまでに少なくとも3ヶ月はかかると言われています。
失敗する人が陥りがちなのは、張り切ってストイックな筋トレ計画を立てて、続かなくなってしまうこと。自分の無理のない範囲で、継続的にトレーニングをすることが重要です。
コツコツとトレーニングを積めば、いつか必ず厚い胸板、たくましい体が手に入ります。
「筋トレを始めてよかった」と思えるように根気強く鍛えていきましょう。



